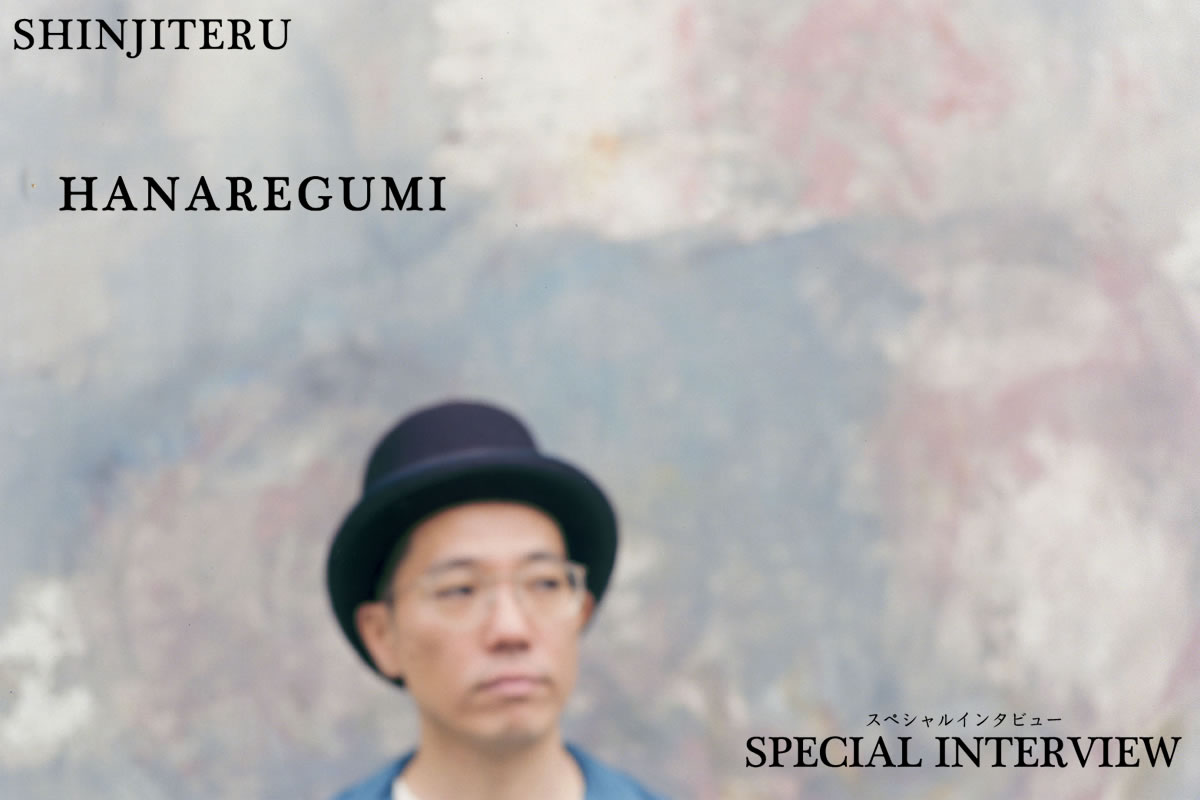
ハナレグミ『SHINJITERU』
スペシャルインタビュー(聞き手:渡辺祐)
ひとりつぶやくような、誰かに囁くようなナンバー「線画」で幕を開けるハナレグミのニュー・アルバム『SHINJITERU』。聴き進めれば、どこか静かで、おおらかで、でもせつなさに満ちたセンチメンタルな景色が描かれていく。映画『海よりもまだ深く』の主題歌となった『深呼吸』をはじめとする作詞作曲を自身が手がけたナンバーに加えて、今回は堀込泰行、阿部芙蓉美、かせきさいだぁ、沖祐市が詞曲で参加。竹中直人の佳曲『君に星が降る』(作詞:竹中直人 作曲:坂本龍一)のカヴァーも収録された。
「4月くらいです。ライヴハウスツアーをやって、その前後くらいから徐々に。でも、前回のアルバム『What are you looking for』で録っていたけど、その時は入れられなかった曲もあったんですよ。沖さんとかせきさんに書いてもらった『秘密のランデブー』とか。『君に星が降る』や『ののちゃん』も原型のようなものはだいぶ前からあったんです。なんか今年を逃すと、この曲たちを出すタイミングがなくなるような感じがすごくあったんです。今年中に出さないと、なんかいけないぞ、ピピピみたいな(笑)。」
──ピピピの部分は、言葉では説明しづらいかもしれないですね(笑)。「うん。『秘密のランデブー』も、すっごくいい曲で、すっごい気に入ってたんですけどね。でも、その時はこのアルバムじゃないなあと思って。今回、この形になったときに、ああ、やっぱりすごくいい判断だったなと思いましたね。」
──この2年の間、次のアルバムにはどんなイメージを描いていたんですか。「うーん……それが、あったような、ないような。前回のアルバム『What are you looking for』と、そのツアーぐらいから、いい意味でいままでのハナレグミが終わっていって、また次に行こうとする、過渡期的なことを感じてたんですよ。音楽のとらえ方というか考え方というか、自分のなかで漠然としていたものが、だんだん具体的になってきたような気がしますね。」
──実際にはどう変わってきたんですか。「まず、歌い方とか歌のイメージですね。前はその世界に聴き手を巻き込んでいくという歌い方だったと思うけど、むしろ歌に入ってきてもらう、思わず入ってきたくなるような歌を歌いたいなあと。うまく言えないですけど、曲を完成させるために歌いたい、歌を曲に捧げたいんですね。聴き手がイメージしたくなるような歌をストーリーテリングしたいなという。テクニックだけみたいになってしまうと、歌は死んじゃうのかなあって。」
──かなりテイクも重ねているんですか。「例えば『線画』は何10テイクも歌いましたね。あと、阿部芙蓉美さんが歌詞を書いてくれた曲は、彼女なりの世界観があるから、こういう主人公で、ここはこういう歌い方のほうがいいというのをディスカッションしながらつくりましたね。新たな人と共作したときに、ああ、こういうふうに曲を完成していくやり方があるんだなと、ものすごい発見でした。」
──それも含めて「過渡期的」なトライがあったわけですね。「ここ二作は、ホントに歌い方はいろいろトライしてますね。パワフルな声で持っていくというのも自分のやり方だし、もちろん好きなんですけど、どこかに一時期までやってきた歌い方を手放したいなあという思いがあって。いまはもっと何かの感情を描くためにはどう歌えばいいかを考えて歌ってますね。」
──それが「歌がうまい」ということの本質なのかもしれないですね。「前はどこかハッピーでいたいって言うか、『イエーイ!』みたいな部分が前に出てたんだけど(笑)、今は『音楽』をより意識しはじめたような気がするんですよ。ただ演奏がうまいとかいい曲っていうことじゃなくて、もっと深度を求めたいって言うか。自分の音楽を客観視するようになってきて、伝えるとか届けるということをもう少し意識しはじめたのかもしれないですね。ただ、いままでやってきたものを、ある意味で手放さなきゃいけない瞬間があって、そうすると自分の中で帳尻が合わないというか(笑)。」
──ということは、このアルバムは、どこかでハナレグミの現在地を見つめ直した。「自分の場合って『こういう方向に進もう』って決めるタイプじゃなくて、いろんな感覚が同時に点在しているんですよ。いまもいろんなことを……たぶん何年か先に結実しそうなことを同時に考えているようなところがあるんですね。『俺はなんでこんなことに引っかかっているのかな?』っていうことがいっぱいある。だから『What are you looking for』くらいから、なんとなく漠然と散らばっていた点が、このアルバムでかなり結実してきたりしてますね。」
──漠然としていたことを形にできるようになった。「そうですね。言葉にしづらいんですけど(笑)。だから自分で作詞作曲をするだけではなくて、沖さんとかかせきさんとか、阿部芙蓉美さんとか、堀込泰行くんとかも入ってもらって、いろんな人を巻き込みながら作っているのが、前作と今作。やっぱり刺激的なんですよね。」
──特に阿部芙蓉美さんは大活躍ですね。「彼女の言葉の使い方がすごく好きだったし、彼女の世界観と自分の声は絶対合うだろうなあと思ってたんですよ。彼女の書く詞って、どこか少年ぽくて、どこかユーモアもあって。『歌詞のメッセージってなんだろう』っていつも思ってるんだけど、言葉で『こうだぜ』って言うことって、果たしてメッセージなのかなって。僕は誰かの景色が立ち上がるような言葉のほうが大事なのかな……。自分の声は、きっと何かの景色を立ち上がらせる素養を持ってるような気がするので(笑)。」
──他のアーティストに曲を頼むときは、どれくらい何を伝えているんですか。「『こうしてください』というのは、最初はまったくないですね。頼む時点ですごくリスペクトしているし、好きな人たちばっかりだから。ただ、できるだけ一緒に時間を過ごすというか、いろんなヒントを渡すというか、それは心がけてます。特に阿部芙蓉美さんの歌詞に関しては、初めて一緒にものをつくるから、どういう風につくることが、彼女のやり方なのかなというのを知る必要もあったから、何度か会って。もちろん、そこに何かしら自分を投影してもらいたいなあというところもあるんです。まったく切り離されたものじゃなくて、どこかしら自分の断片が彼女の脳みそを通って反映されてほしいなと思っていて。僕がよくやるのは、日々書き留めている数行の言葉みたいなのがあって、そういうのを全部見てもらう。超ダサイことを言ってるとか、恥ずかしいのとかも(笑)、全部見てもらって、そのなかで引っかかった言葉をやり取りしていって、『これってどういうことなのかな』って話をしたりとか。」
──そんな積み重ねを象徴する言葉がタイトルの『SHINJITERU』ということですか。「いや、『SHINJITERU』というタイトルは、アルバムをトータルして象徴している言葉というよりは、単純に遊びとして、いま『信じてる』という言葉を世の中にバラまいてみたいなと思ったんですよ(笑)。でも、僕が『みなさん、信じたほうがいいよ』なんて言うわけじゃなくて、さっき言ったみたいにひっかかるものとして何年か前から『信じるってどういうことなんだろう』というのがあったんですね。実は半分寝てるときに『SHINJITERU』『DASAI』『OYAJI』って、全部アルファベットで浮かんできて、『なんだろ、これ?』とか思って書き留めてたんですよ。それを阿部芙蓉美さんに見せたら、『SHINJITERU』ってアルファベットで書くと、超イイっすね、っていう話になって。先にタイトルを投げてから、そこに自分が追いつくみたいになるんですけど。」
──そこには時代に対する感覚みたいなものも働いていますか。「そうかもしれないですね。自分も音楽やってて、どんどん世の中変わってきて、追いつけないことが多いというか。例えばもうパソコンのなかで音楽が成立しちゃうとか、そういうことを自分なりにどう理解したらいいのかなとか、まだはっきりできてないことが多くて。イマジネーションを膨らませたり、何かをつくったりするということは、心を全部開かなきゃいけないじゃないですか。だから変わることに対しても飛び込むような気持ちもあるし、怖さもあるという。それは音楽に限らず、いまは世の中がガーッと変わってきてるじゃないですか。自分たちを取り巻く状況も、前はこんなこと絶対起こらなかったようなことが起きますよね。『そんなこと言っちゃっていいんだ』とか『こんな突然携帯電話から警報が鳴るんだ』とか。だから自分を維持していくのがしんどくなっちゃうと言うか……。でも、やっぱり手放せないじゃないですか。じゃあ何が変わらずに自分のそばにあるものなのかなと、いつも考えるんですけど、そうすると結局『自分』だけなんですよね。絶対に何も裏切らないというか。だからこの『信じる』という言葉は、遠くのものを信じるというよりかは、全部自分のなかにあるということかな。」
──そういう意味では、収められた曲のタッチとジャケットもすごくリンクしていますね。「今回、ジャケットの角田純さんにお会いして、描いていただいたということが、自分にとって大きかったですね。一曲一曲つくっているときには漠然としていたことが、最終的にジャケットでお願いした角田さんにお会いすることによって『ああ、やっぱこういうことだったんだ!』ってまとまった。実は、この数年、『線』というものに興味があって。」
──曲目に収められた「線画」がそれですね。「何年か前に漫画家・井上雄彦さんの『スラムダンク』のドキュメンタリーDVDでナレーションをやらせてもらったことがあって、すごく感動したんですよ。どんなプロの人でも、まず一本の線から始まる。その線は誰もが描ける、俺だってチビッコだって描ける線で、でもその線をひとつの意思を持ってずーっと積み上げていくと、感情になって現れてくるというか。『バガボンド』でも例えば武蔵が無言で立ち尽くしているカットが数カットつづいてく、ぱっと見るとそれぞれのカットでどこが変わっているのかはわからないけど、確かに主人公の気持ちが移ろっていくのがわかる。その感情の移ろいをさえ線で生んでしまうということに気がついた瞬間、すごく感動して。その何年か後に浦沢直樹さんのアトリエに行かせてもらう機会があって、原画を見せてもらったときにも凄かった。原画じゃないとわからないものってあるんですよ。たった1枚の1ページ1コマに、どんだけ命込めてるのかなって感じるくらい、怖いくらいに迫力があって。」
──原画や絵画の現物って、本物だけが持っている凄味がわかるんですよね。「そう。セリフがなくても、圧倒的な何かがブワーッと鳴ってるんですよ。それとは全然比べられないですけど、自分でも点描画を描くことが、最近急に始まっちゃって。ブルースやソウル、レゲエなどのブラックミュージックが大好きなので、彼らミュージシャンの写真を点描で描くことでその人たちの体温に触れられたような気になってくるんです。何時間もかけて点を積み重ねて顔を描いていると、なんかその人の性格までわかるような気がしてくるというか。」
──「深呼吸」のジャケットで自画像を描いてましたね。「あの絵を描いた時、自分のカッコつけてる部分とか、気の弱さとか、顔のいろんなところに点在してることに気がついたんですよね。それで思ったのが、もしかしたら人間って、誰かにパッと会ったときに『こういう人なんじゃないか』って最初に感じとったものって、実は大正解なんじゃないかって。人間の目って大雑把に見ているようでいて、顔の細かな線や点まで知覚してるのかもしれないと思ったんですよ。もしかしたら人間も全部『点』や『線』でできていて、それが積み上がっていくこと、それを信じたいと言うか。線が重なっていくことで生まれてくる何か。そこから何かを受け取った自分のなかに、正解が生まれるというか。」
──それがさっきの「ああ、やっぱこういうことだったんだ!」につながる部分ですね。「たまたま友達が教えてくれた角田さんが線を使って描いている『SOUND AND VISION』という作品集を見たときに、きっとこれって言葉になる前の言霊の模様なんじゃないかって感じたんです。言葉になる前の言霊ってこのような模様をしている物で、それらが浮遊していたのじゃないかって思って。角田さんにお会いしてその話をしたら『まさしく自分もそういうことを思って描いたんだよ』って。」
──『SHINJITERU』というタイトルの深みがわかってきた気がしますね。「『信じてる』っていう言葉って重いじゃないですか。『私、あんたのこと信じてるから』って、すごい強い言葉だけど、そうじゃなくて、言葉に落ちてくる手前の『何か』を信じてたらいいんじゃないかって。そういう意味もあって、今度はジャケットも『SHINJITERU』っていう文字を印刷でデコボコさせて、言葉だけを受け取ってもらうのじゃなくて触感するような意味になって届いたらいいなと思いそうしました 。そういう物語に今回の音を全部入れたかったんですね。この曲たちが生まれた時間っていうのは、自分がそういう漠然としたことを拾い集めてきてた時間と重なっているわけですから。」
──「歌への想い」や「点と線」の話からうかがえるのは、やはり深まることへの希求ですね。「そうですね。その感じは、前作もあったと思うけど、でも、今作のほうが、より自然体かなあ。あまりショーアップしないというか。イマジネーションすることが強さだと僕は思っていて。どんなにハイヴィジョンになって目の前に、どこか知らない大地がきれいに映っていても、そこに自分のイマジネーションが足されていかなければ、何も立ち上がってこないような気がしてて。それで言えば、イマジネーションとしての『せつなさ』というのは、力だと思うんですよ。せつなさって、遠くのものを近くに呼び寄せるじゃないですか。ハッピーはこの目の前の瞬間で消化されているけど、せつなさって遠くのものが目の前に立ち上がってくる。一曲目の『線画』で歌ってるけど、『背中合わせで見上げる空』ですよね。」
──「せつなさ」はこのアルバムの感触の大きな部分だと思います。「対面して何かを共有しなくても、背中で遠くのものを感じて、同じ空を見つめていることほど、重なり合ってることってないんじゃないかなっていうのが、自分の根本にずっとあることで。そういうことをこの街というか日々にあえてぶち込みたいというか……。なんかね、どんどん世の中が形相的にハッピーになっていくことに、どこか腹立たしさを感じて(笑)。」
──そこも引っかかっていた。「あと距離感がないこともそうですね。何かを取り込むには、僕は人や物事との距離感って、ものすごく大切じゃないかなと思うんです。それがパッと見てパッとわかった気になってしまうと、そんな速さでものと向き合っていたら、本当にひとりに、孤独になっちゃうんじゃないかって。そんないろいろ引っかかってきたことに答えを出したい……そう考えると、このアルバムは、自分なりの、すっごい些細なパンクです(笑)。」
──せつないという攻めをしている「せつなさパンク」(笑)。「そう(笑)。せつないこととか悲しみというものを大げさにもしたくないし、遠ざけたくもないというか。フッとわき上がるそういうものを、いい距離でいつもそばに持っておかないと、危ない気がするというか。特にライヴだとすごくその部分がシンクロするんですね。ライヴを見にきてくれた方に『大勢がいるライヴの会場なのに間奏になった瞬間にまるでひとりっきりになったような気持ちになりました』と言われたことがあって、それはその通りって思った。どこかでそうじゃないといけないと思っているというか。音の向こうに自分を見るような瞬間があってほしいし『そうなってしまえ』と思ってるところもあって。こういう言い方が正しいかどうかわからないけど、せつなさや郷愁は、誰から教わらなくても、そこで体がエモーションしてしまう。僕はその感情は、すごく強さだと思っていて。」
──せつなさが強い、というのはパンクであり、ブルースですね。「そうかもしれない。僕は自分が生まれ育った環境にブルースはないと思っていたし、それが黒人アーティストへの憧れにも繋がってきましたけど、実はここから先は、そういう見慣れた景色のなかにブルースが立ち上がってくるのかもしれないですよね。是枝裕和監督の『海よりもまだ深く』にもそれを感じましたね。しかも、そのブルースは、過去を懐かしむようなことではなくて、なにか次に繋がるような感覚でありたいとも思うんです。ここ何年かを考えれば、やっぱり東日本大震災が大きいじゃないですか。その余波というか、その思いのなかから、何かの始まりがある。『本当に始まるぜ』っていう余韻を、このアルバムにはどうしても入れたかった。ただせつなくなるだけじゃなくて、そのなかにひとひらの光が絶対あるというようなものに。だから『安心してせつなくなっていいぜ』と言うか、安心できるせつなさを提供したいというか(笑)。」
──「安心できるせつなさ」っていい言葉ですね。「秋になったら金木犀が香ってくるとか、春になったら沈丁花とか、そういうものと同じものを持たせたいと言うか。それで十分だし、僕の好きなのはそこなので。抽象的だけど、いろんなことが叶わなかったとしても、真ん中だけは何かを残したいって思うんです。特に今回は、ある種の熱量で、そういうものになりたいと思った。そういう歌を歌っていくシンガーでいたいんですよね。」
──純粋なシンガー・ソングライターとしての「永積 崇」ではなくて「ハナレグミ」を名乗っている意味がそこにあるような気がします「そうなんです。歌い手になりたい。自分のなかでシンガーという比重は大きいなあと。それもこの二作で明確になりましたね。」